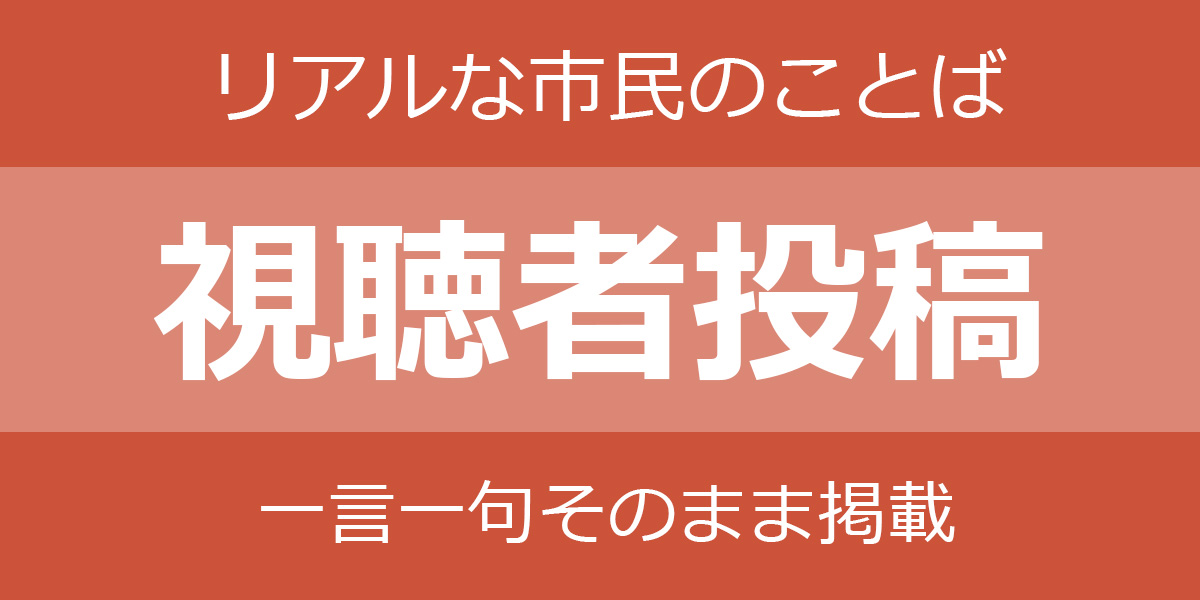源泉交湘さんからの投稿
『大阪・関西万博』は、「いのち輝く未完社会のデザイン」をテーマに、未完の展示館を残しながらも、4月1 3日晴れやかに大阪夢洲で開幕した。未完の展示館はいずれ遅ればせながら開館して賑わいに貢献してくるに違いない。
しかし、当舞鶴市の「中央図書館」の建設計画は、「思い描く図書館づくり」として、’’実在感のない’’キャチフレイズの碁、当局の思いに沿った形で、住民との意見の乖離をものともせず進捗しつつあるように見受けられる。これはなぜなのか?
古くからの諺に「本を務む。本立ちて道生ず」(論語)・・・人はすべて、なにごとについても、末梢のことや、形だけにとらわれないで、根本を把握するように努力すべきであり、根本のことをやっていれば、あとは自然に方法は立つものだ。・・・とあるように、最初の出発点からの誤りが是正されぬまま強引にことを推し進めようとしているためと観察できる。
その一つは、利用者である住民の意見を無視するようなかたちで、‘‘分館ありき”、“夢のよ うな中央図書館ありき’’で、まるで絵空事の図書館を夢見させて、議論を無理やり推し進める高圧的な姿勢に由来している。
また、当局はワークショプを開いて住民の意見を吸い上げたように演出しているようであるが、ワークショプは意見を‘‘聞いた感’’を演出するだけの装置として利用しているだけで、当局の本心は市民に説明せず都合よく聞き置くガス抜きに利用しただけだった。
そもそも、なぜ議論の基礎的部分を飛ばして“分館ありき’’から議論を始めたのだろうか?艤論は段階を踏んで先ず図書館を除去することが正しいかどうかの選択を、正直に話し合うべきであった、にも関わらず、課題の某礎部分を意図的に省略して
「’‘夢に描く’’図書館つくり」から話題を進め、‘‘実在感の無い”まま絵に描いた餅(計画)を既成事実化することで、持論の「夢」を現実化すべく議論の展開をなぜか急いでいる。
‘‘図書館除去’’は大きな争点になることを見越して、争点にならぬよう姑息な配慮をしたと指摘せざるを得ない。
議論すべき段階を飛ばして’’除去’’が話題にならぬよう、ずる賢く配慮した。括礎部分を固めないまま建築物を組み上げたような状態で議論を急いだことで、以後の組み立てを不安定にしてしまった。
しかもこのことを意図して行うことで、自らの持論(中央図書館ありき)を最速で達成しようと策略していることであり、其のことは市民との熟議を否定しているに等しいことだ。
また、このことは既成事実を先行して先を急ぐ姿である。
昨年末まで「夢のような図書館作り」のワークショプを開いて市民の意見を集めていたと思いきや、その結果をとりまとめる間もなく『広報まいづる』一月号には図書館甚本設計計画の内容が公表された。
このあまりにも手回しの良さは、すでに中央図書館の甚本設計は当局には以前から出来上がっており、当局案のアリバイ造りのためにワークショプを開催したりなどして、持論の正当性を演出していたことを示すものに他ならない。
今まで当局が行ってきたワークショップや懇談会は、手の込んだ当局の目くらましに過ぎない猿芝居だった。